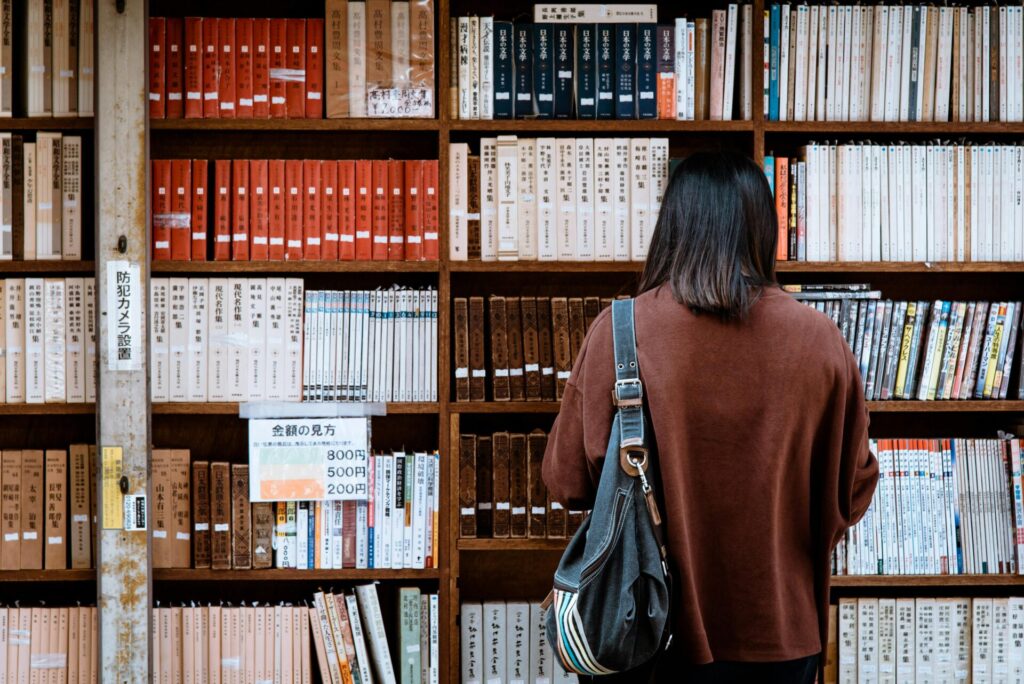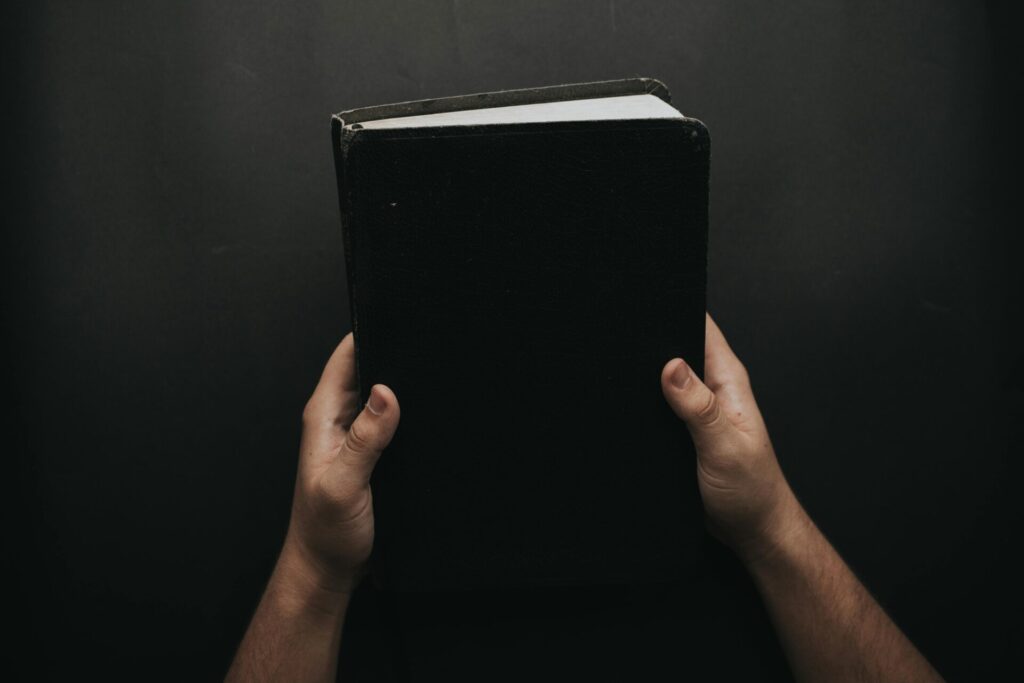読まない社員を巻き込む読書研修の仕掛け ── 自発的な学びを生み出すデザインとは

「社員に本を読ませても、結局読まないまま終わってしまう」── そんな声は多くの企業で聞かれます。 しかし、本を読まないのは意欲がないからではなく、“読める環境と仕掛け”が整っていないからかもしれません。
この記事では、リーディング・シェア研修や社内読書会を成功に導くための「読まない社員を自然に巻き込む仕掛け」をご紹介します。
目次
「読まない社員」が生まれる3つの理由
- 時間がない:業務が忙しく、読書の優先順位が下がる。
- ハードルが高い:ビジネス書に苦手意識がある。
- 目的が見えない:読んでも仕事に活かせるイメージが持てない。
この3つの要因を乗り越えるには、「読ませる」よりも“巻き込む設計”が必要です。
巻き込みのための3つの仕掛け
(1)読む負担を減らす:要約・音声・分担
「1冊を読む」から「1章を共有する」に変えるだけで参加ハードルは大きく下がります。 最近はAudibleなどの音声読み上げや要約サービスも充実しており、移動時間でも学べます。 リーディング・シェア形式で分担読書にすれば、読書がチームプレーに変わります。
(2)“語る場”をつくる:読むより話すを中心に
「読んでいなくても聞くだけで参加できる」仕組みをつくると、非読書層の参加率が上がります。 読書会では「印象に残った言葉」「自分の仕事とつながる部分」などをテーマに短く語り合うことで、読書が体験的な学びに変わります。
(3)小さな成功体験を設計する
読書が苦手な人にとっては「最後まで読めた」「一言発言できた」という成功体験が次のモチベーションになります。 ファシリテーターは「読まなくても参加できる」「話したくなる空気」をつくることが大切です。
実際に成果を上げた企業の工夫
- 広告代理店A社:読書が苦手な社員向けに「1ページ読んで気づいたこと」を共有する形式を採用。最初の3回で参加率が60%から92%に上昇。
- 金融B社:毎月1冊を要約した資料を人事が作成。各チームで5分間ディスカッションするだけの仕組みにした結果、「研修が日常化した」との声が増加。
- IT企業C社:Audibleで同じ本を聴きながら、Slack上で感想スレッドを投稿。リモート社員も参加できる「音声読書会」として定着。
いずれも共通しているのは、“読まなくても参加できる入口”を設けている点です。 参加しているうちに自然と「次は読んでみよう」と思える流れをつくることが重要です。
モチベーションを維持するための「共有設計」
読書研修を継続するコツは、“読書の成果”を可視化すること。以下のような方法がおすすめです。
- 読後コメントをGoogleフォームやSlackに投稿し、月次レポート化
- 優れた発言・気づきを「社内ニュースレター」に掲載
- 年1回「この本で変わったこと」プレゼン大会を開催
共有することで学びが社内に広がり、読まない社員も「自分も一言言ってみようかな」と関心を持ち始めます。
読書を「文化」に変える最後のステップ
読書研修のゴールは「全員が本を読むこと」ではありません。 本を通して考え、話し、共感し合う文化を育てることが目的です。
本を読まなくても意見を言える場を設ける。 一章だけでも学びをシェアする。 その積み重ねが、組織の中に“学び合う空気”を生み出します。
やがてそれが、自然と本を手に取りたくなる環境── 「読まなくても参加できる」から「読みたくなる文化へ」と変化していくのです。
まとめ
- 「読まない社員」は意欲がないのではなく、環境設計が不足しているだけ
- 要約・音声・分担など“軽量参加”を導入する
- 読むよりも「語る場」「共有の仕組み」を重視
- 読書の成果を見える化し、成功体験を積ませる
- ゴールは“本を読むこと”ではなく“学びが循環する文化”を育てること
強制ではなく、巻き込み。 それが「読まない社員」を動かし、チーム全体を成長させる最もシンプルで強力な方法です。